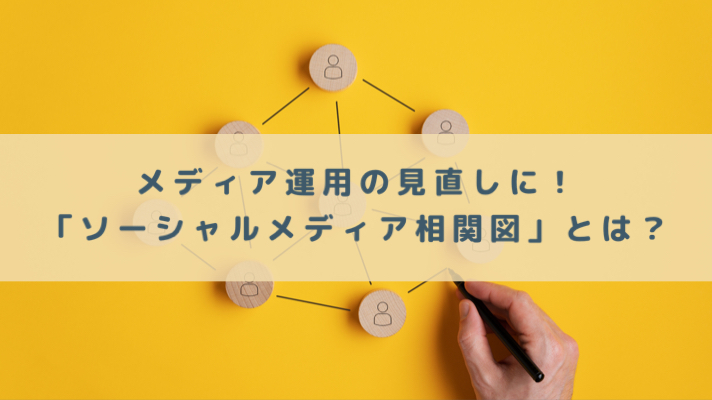
こんにちは!
継続的なメディア運用とコンテンツ作成をサポート津田麻美恵です♪
それぞれのメディアをどのように使うのか
を考えることが重要です
そのための第一歩として
ソーシャルメディア相関図を作成してみるのはどうでしょう?
この記事では、
ソーシャルメディア相関図について
メリットや作り方などの情報をまとめています
もくじ
ソーシャルメディア相関図とは?
全てのメディアの相関関係を視える化した図
まず初めに、
ソーシャルメディア相関図とはなんでしょう?
この記事を読んでいる方の多くは
「ソーシャルメディア相関図」と言う名前を
初めて聞いたと思います。
と言うのも、
「ソーシャルメディア相関図」は
コンテンツ作成について学ぶ中で
私自身で形としてまとめたものです
もちろん、
似ているアイデアを持っている方は大勢いると思いますが
「ソーシャルメディア相関図」と名前をつけているのは
私くらいかもしれません
それでは、ソーシャルメディア相関図とは何なのか?
それは、その名の通り
運用しているメディアを視覚的にまとめた図
というのが最も簡単な説明です
「ソーシャルメディア」と名前がついていますが
SNSやブログ、ウェブサイトといった
オンラインメディアだけでなく
情報誌のような紙媒体から
動画や音声配信に至るまで
自分が情報発信を行なっている全てのメディア
を相関関係と共に書き出したものが
ソーシャルメディア相関図となります
詳しい構造や作り方は、
この記事の後半で解説しています
ソーシャルメディア相関図が必要な理由
それではどうして、
ソーシャルメディア相関図が必要なのでしょうか?
「自分が運用しているメディアくらい、把握している」
そう言う方は多いと思います
ですが、複数メディアを運用していて
なおかつ、ビジネスに繋げたいと思っているのなら
「どんなメディアを使っているか?」よりも
「どんな風にメディアを使っているか?」の方がより重要です
毎日投稿しているのに、
お問い合わせはおろか、フォロワーすら増えない
そういった悩みは多くの事業主様が経験しています
複数メディアを効果的に運用するには
それぞれのメディアの特徴を理解しながら
どのように使っていくかを考える必要があります
そのために、
ソーシャルメディア相関図は
俯瞰的な視点を提供してくれるのです
複数メディアを運用する負担
この記事を見ている方の中には、
メディアを複数使っている方も多いことでしょう
私も、過去には10個近いメディアを
同時に使っていたことがありました
たくさんのメディアで情報発信をすれば
それだけ人に見てもらう機会も増えていきます
そのため、複数のメディア運用は
ビジネスの成長を促すためにも必要なことと言えるでしょう
ですが、それと同時に負担も大きくなります
「全てを1人で運用しきれない」
そのように感じている事業主様は
あなただけではありません
1つの投稿を作るにも、時間と手間がかかります
しかも、毎日投稿するとなれば、「ネタ」の準備も必要
またメディアによって投稿様式が違うので
メディアごとに編集をする場合も・・・
運用するメディア数が増えれば増えるほど
事業主様の負担も増していきます
また、多くのソーシャルメディアは
それを使うこと自体は無料でできますが
投稿を作ったり、コメントに返信するための
時間や手間がかかっており
これらは、紛れも無く経費がかかっています
目には見えなくとも、
複数メデイアの運用を1人で行うとなれば
かなりの負担になると言えるでしょう
負担が増えれば、運用は続かない
「無料で使えるから」と聞けば
アレもコレもと使って見たくなるソーシャルメディアですが
実際には、時間や手間といった経費がかかっています
しかも、広告を出すとなれば広告費もかかります
ところが、ソーシャルメディアというのは
手間暇をかけたからといって
その効果がすぐにわかるものではありません
今日、あなたの投稿を見たユーザーが
その場ではあなたの商品/サービスを購入せずに
半年後、あなたのことを思い出して購入に至る
ということはよくあります
このように、
ソーシャルメディア運用における最も大きな負担は
目に見える効果がわかりにくいということです
効果がわかりにくい上に、時間も手間もかかる
運用の負担が増えた結果
多くの事業主様が継続的な運用ができずにいます
仮に運用できていたとしても
計画性がないまま運用しているせいで
思ったような結果を得られていないことも多々あるのです
ソーシャルメディア相関図で出来ること
そこで活用していただきたいのが、
今回紹介するソーシャルメディア相関図
ソーシャルメディア相関図があれば
- メディア運用全体を俯瞰的に考え
- どのメディアに注力すべきかがわかり
- メディアに応じた情報発信がわかる
これらのことが実現できるようになるでしょう
ソーシャルメディア相関図を作ることで
得られるメリットを紹介していきます
ソーシャルメディア相関図を作るメリット
次に紹介したいのは
ソーシャルメディア相関図を作成することで
得られるメリットです
ソーシャルメディア相関図は
運用しているメディアをただ書き出しているだけではなく
それぞれの相関関係もわかるように作っていきます
ソーシャルメディア相関図があれば
メディア運用全体を俯瞰して、今、注力すべきメディアを見つけ
それぞれのメディアに応じた情報発信を考える
そういったことが簡単にできるようになるのです
ソーシャルメディア相関図を作るメリットを
さらに詳しく見ていきましょう
メディア運用を俯瞰して考えることができる
ソーシャルメディア相関図を作成することで得られる
一番のメリットは、メディア運用全体を俯瞰して捉えることができること
複数メディアを運用している事業主様の多くは
「自分が運用しているメディアは当然把握している」
と言う方が多いと思います
しかし、実際に詳しく伺っていくと
どのメディアを使っているのかを列挙することはできても
それぞれのメディアをどのように使っているのかまでは把握できていない
つまり、メディア同士の相関関係がわからない方は多いのです
例えば、X(元Twitter)と公式LINEを使っている場合
Xのプロフィールに公式LINEへの登録リンクを貼り付けているのですが
それぞれのメディアで同じ内容を発信していたり
まったく関連のない内容を投稿していたり・・・
このように、
メディア同士がただつながっているだけでは
ユーザーが公式LINEへ登録する理由がありません
また、発信されている情報に対して
価値があると感じてもらうことも難しくなるでしょう
複数のメディアを運用する際には
それぞれのメディアでユーザーとどんな関係を育てたいのかを考え
発信する情報を決めていきます
そして、ユーザーとの関係に応じて
適切なメディアへとユーザーを誘導していきます
そうすることで、
最適な情報を、最適なタイミングで、最適な人へ届ける
ことが可能になります
ソーシャルメディア相関図を作れば
どのメディアで、どんなユーザーに向けて、
どういったコンテンツを発信しているのかが
一目で分かるようになるのです
どのメディアに注力すればいいのかわかる
運用するメディアの数が増えれば
より多くのユーザーにあなたの情報が届きます
その一方で、
私のように1人で複数メディアを運用する場合
全てのメディアにエネルギーを等しく使うことが難しくなります
メディア運用を行うことが私の仕事ではありません
それなのに、メディア運用に多くの時間と労力を使えば
クライアントとのミーティングや資料作成をする時間がなくなり、
さらには、大事な家族と過ごす時間さえもなくなります・・・
そこで重要になるのが
今、力を注ぐべきメディアを決めること
つまり、優先順位をつけるのです
あなたは、
「どのメディアも平等に頑張らなくてはいけない!」
そう思いながらメディア運用を頑張っていませんか?
全てのメディアに時間と労力と使うことができる・・・
それは理想の運用であり、
頑張った分だけの結果が出るかもしれません
ですが、
全てのメディアを頑張らなくてはいけない
というルールはありません
どのメディアを中心に使うのかは、
あなたが決めてもいいことなのです
私の場合、
全てのメディアで投稿するネタ元になるのは
こちらの公式サイトで書いているブログです
ココがしっかりできていれば
他メディアでの情報発信が格段にはかどります
とうことは、
私が最もエネルギーを注ぐべきメディアは
公式ブログということになります
InstagramやYouTubeチャンネルも持っていますが
それらのメディアは、
私にとって優先順位が低いメディアなのです
あなたの場合はどうでしょう?
情報発信の目的を思い出しながら相関図を丁寧に見ていくと
ポイントなるメディアが見つかると思います
見方を変えれば、
使わなくていいメディアがわかることになるので
複数メディアを運用しているのであれば
思い切って「辞める」メディアを決めてしまいましょう
そうすることで、
主力となるメディアに使える時間や労力を確保できるのです
ソーシャルメディア相関図を作ることで
あなたが使うべきメディア
あるいは、辞めるべきメディアを決めていきましょう
どのメディアを使っていくのか?を決める際には
こちらの記事でメディアの種類について解説しているので
参考にしてください
コンテンツ作りはあなたの仕事ではない
私がよくクライアントさんにお伝えしているのは
「コンテンツ作りがあなたの仕事ではありませんよ」ということ
コンテンツを作り、情報発信を続けるのは
認知を広げたり、新しい顧客と出会うための下準備
つまり営業活動となります
しかし、売上に目を向けた時
営業活動が売上に直結することはありません
商品やサービスを提供して初めて、
代金をいただく、つまり、売上になります
1人で事業を行っているのであれば
メディア運用ばかりに時間を取られていても
売上が上がることはないでしょう
また、
コンテンツ作りが営業活動だと勘違いしている
そういった事業主様も多くいます
営業活動はコンテンツを作って投稿するだけではありません
集客や売上に必要な事は他にも無いか
ご自身の状況を確認するためにも
ソーシャルメディア相関図はおすすめです
どんな情報を発信すればいいのかがわかる
あなたのアイデアを発信することができるメディアは色々あります
ですが、情報発信を行う際に気をつけるべき事の1つが
それぞれのメディアの特性を理解して発信するということ
例えば、
画像による情報発信だとInstagramが有名です
オシャレで目を引く画像がメインで
日本国内でのアクティブユーザーは30〜40代の女性です
また、投稿方法(配信面)もいくつかあって
画像だけでなくショート動画やライブ配信も可能
さまざまなメディアのいいとこ取りができるSNSと言えます
画像がメインとなるSNSなら、Pinterestもあります
ところが、こちらは情報発信よりも
「情報をまとめる」ことが得意なメディア
カテゴリーごとに情報をまとめれば
デジタルカタログとして使うこともできます
このように、使用するメディアによって、
発信方法やユーザー属性、メディア内の雰囲気など
それぞれに特徴が異なっていますね
ソーシャルメディア相関図を作ったら
自分の情報発信は利用メディアの特性とマッチしているのか?
改めて確認してみるのがおすすめです
情報発信というのは、
以前のように発信すれば誰かが見てくれる
というものではなくなりました
視聴するユーザーの好みが反映させるアルゴリズムが主流となったことで
ユーザーが求めている情報を発信することが重要です
ソーシャルメディア相関図を元に、
どんなユーザーにどんな情報を届けるべきかを考えましょう
そうすれば、コンテンツを生かしたメディアが選べます
ソーシャルメディア相関図は2種類ある
以上のように、
ソーシャルメディア相関図を作ることで
メディア運用を俯瞰して考えることが出来るようになり
力を入れるメディアはどれなのか、どんな内容を作ればいいのかまで
具体的に考える助けになるのです
それでは、
ソーシャルメディア相関図は
一体、どんな構造をしているのでしょうか?
実は、ソーシャルメディア相関図には
マインドマップ型(平面タイプ)と
ファネル型(逆さピラミットタイプ)の2種類あります
それぞれ、異なる特徴があるので
2種類を作成しておけば、メディア運用を多角的に考えることができます
さっそく、それぞれのタイプを解説していきましょう
「流れ」が見える平面タイプ
最初に紹介する相関図は
マインドマップ状にメディアを配置していく平面タイプ
このタイプの特徴は
使用しているメディアを全て書き出した後に
理想のユーザー導線とメディアの相関関係を
線と矢印を使って表現していきます
出来上がると、
まるでマインドマップのように
運用しているメディア同士が線で繋がれ
現在のメディア運用の状況が一目で確認できる図が完成します
平面タイプを作成するメリット
平面タイプのソーシャルメディア相関図を作るメリットは
主に以下の2つがあります
それぞれ解説していきます
フォロワーの流れ(メディア導線)を可視化する
平面図タイプの相関図では
ユーザーが各メディア間をどのように動いているのかを
わかりやすく捉えることができます
理想の形であっても、
ユーザーにどのような順番でメディアを周回し
それぞれのメディアでどんな情報を得て欲しいのかをイメージすることで
各メディアにどういったコンテンツを載せればいいのかも
計画しやすくなります
現在使っているプラットフォームの整理ができる
平面タイプの相関図を作るメリットは
今あなたが使っている全てのプラットフォームやメディアを
俯瞰できる、つまり、「視える化」できることです
複数のメディアを運用していると
あまり活用できていないメディアも出てきます
平面タイプの相関図を書き出すことで
どのメディアをよく利用しているのか
あるいは、うまく活用できていない
そんなメディアも見つけることができます
複数のメディアを運用するには手間暇がかかります
そのため、使っていないメディアや効果のないメディアは
思い切って利用を止めてしまうことも必要ではないでしょうか?
そうすることで、
効果のあるメディアに力を入れる時間や労力ができます
一度に全てのメディアを運用する必要はないので
露出するメディアを少しずつ増やしていきましょう
平面タイプを作る時のポイント
それでは、
平面タイプのソーシャルメディア相関図を作る際に
ポイントとなる点を2つ紹介します
メディア運用の目的を意識する
最初のポイントは、「メディア運用の目的」
目的を持ったメディア運用の重要性については
過去の記事でも解説しているので、参考にしてください
特に、平面図を作って使用メディアを書き出している時には
それぞれのメディアが持つ目的や役割を
あなたの理想で構わないので、書き出していきます
そうすることで、
この目的のためにはどんなコンテンツがふさわしいのだろう?と
考えることができるようになるのです
また、メディアの運用目的を考える時は
それぞれのメディアの特徴も意識しておきましょう
メディア導線はできるだけシンプルに
メディア導線を考える時には
メディア同士の関係を複雑にしないことがポイントです
導線が複雑になってしまうと
それぞれのメディアの役割がハッキリしなくなり
「結局、どのメディアでも同じ発信をしている」
という状況になりかねません
複数メディアの運用を成功に導くためには
どこに力を注げば効果的か?を考え、
必要なメディアに必要な時間と労力を充てましょう
メインとなるメディアを介して
それぞれのメディアを訪問できるようにしてもいいですし
複数のメディアを訪問したながら
メインメディアへと集約されていくというのも
導線としてはわかりやすいくなります
「関係」が見えるファネル型
逆さピラミッドは
ユーザーにメディアを周回してもらいながら
「理想のお客様」を見つけ出したり、
より強い関係作りを行うときに便利な図です
逆ピラミッドを作るメリット
ファネル型のピラミッドでは
ユーザーの動きに注目するマインドマップ型とは異なり
もユーザーとの「関係性」に焦点を当てます
理想の関係を育てる
ファネル(漏瑚)という名が示す通り
逆ピラミッドタイプの相関図では
ユーザーを「ふるい」にかけながら
より強い関係を育てるメディア運用を考えることができます
なぜなら、
Instagramのアカウントにフォロワーが1000人いたとしても
その全てのユーザーがあなたにとって理想の顧客とは限りません
長く良好なお付き合いを続けていくためには
質の良い関係を育てていける
「理想の顧客」を見つけ出すことが重要になります
複数のメディアを周回してもらうことで
あなたの理想に近いユーザー(未来の顧客)を見つけるために
ファネル型のソーシャルメディア相関図や役立ちます
作る時のポイント
ファネル型相関図を作る時のポイントは、関係性
つまり、
「今の関係」と「未来の関係」を考えながら
相関図を作っていきましょう
タッチポイントという考え方
ユーザーとの「今」の関係性を考えるとき
それぞれのメディアは
ユーザーとの接点(タッチポイント)であると言えます
そして、ユーザーとの関係性がどのように変化するのかは
どれくらい多くユーザーと接点を持ったのか?
に左右されています
つまり、接点が多ければ
ユーザーとの関係性は深まりますし
反対にあまり接点が持てなければ
関係性はそれほど育たないでしょう
ファネル型相関図を作る時には
ユーザーとの接点がどれくらいあるのか
を意識してみてください
メディアが変われば関係性も変わる
関係構築のためのメディア運用という記事でも触れている通り
ユーザーがあなたの商品/サービスを見つけてから
実際に申し込みや購入といった行動に至るまでに
ユーザーは複数のメディアであなたとの接点を持ちます
例えば、
「ワークショップへの申し込み」の場合
Instagramでワークショップに参加した人の投稿を見る
↓
メンションされていたあなたのプロフィールを確認
↓
あなたのアカウントをフォローする
↓
フィードやストーリなどの情報であなたのことを知る
↓
あなたに対する信頼度が増す
↓
ワークショップの情報に興味を持ち始める
↓
ストーリーでワークショップの受付を知る
↓
申し込む
上の例では、Instagramという
プラットフォーム内での行動と関係性を挙げましたが
1つのメディア内だとしても、
あなたを知ったきっかけは他のアカウントの投稿だったり
プロフィールやフィード、ストーリーといった
複数の配信機能からの情報を受け取りながら
ユーザーとあなたの関係性が育ったことがわかると思います
これは、利用しているメディアの数が増えても同じです
X(元Twitter)、Linkedin、Webサイトという3つのメディアなら
それぞれのメディアを行ったり来たりする中で
ユーザーが抱いているあなたに対するイメージがより具体的になり
関係性が育っていくのです
ファネル型相関図を作成するときには
ユーザーと接点を持つメディアが変わるごとに
どんな関係が育っているのかもイメージしておきましょう
参考YouTube動画
タッチポイントを考慮したファネル型相関図を作る時には
こちらのガイアックス株式会社ソーシャルメディアラボの動画が
わかりやすくておすすめです
今回の記事では
ソーシャルメディア相関図の基本をまとめました
ソーシャルメディア相関図の作成は
トヨタ生産方式における「5S」
つまり、全ての仕組みの基本となる部分です
ソーシャルメディア相関図があれば
この後に作成するコンテントマトリクスや
実際のコンテンツ作りもラクになります
最後まで読んでいただきありがとうございます
この記事の内容をまとめたPDFは、
ダウンロードボタンで確認&ダウンロードが可能です(別ウィンドウが開きます)
PDF資料について
資料の内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
また、まとめサイト等への引用を厳禁いたします。
コンテンツ等の利用については「利用規約」を確認してください。
津田 麻美恵
mamietsuda.comの運営者。個人事業主やフリーランスを中心に、ブログやSNSのコンテンツ作成を指導。また、メイクアップアーティストとしての一面もあり、プロフィール撮影のためのイメージコンサルも行う。コンテンツ作成に関する講座でも、簡単な言葉で理解しやすい説明に定評がある。
この作者による他の投稿も読む
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Facebook
Email
Print
他の記事を読む
おすすめ記事
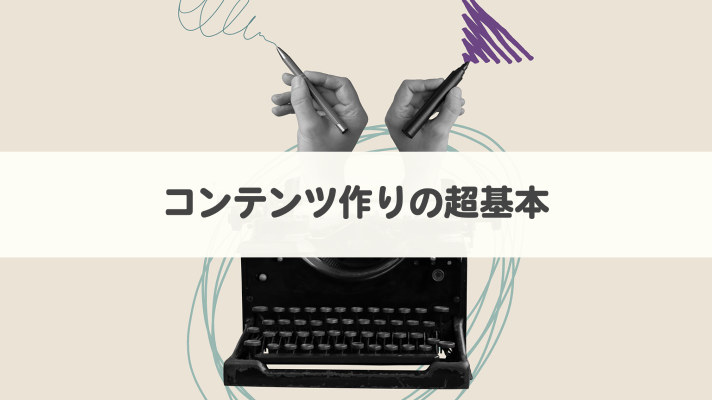
コンテンツ作成
保存版!コンテンツ作りの超基本
Content is king.(コンテントは王様)と言ったのは
マイクロソフトの共同創業者であり、実業家、慈善家でもあるビル・ゲイツ氏
SNSであれ、ブログであれ、動画であれ
どんな方法で情報発信をするにせよ、重要になってくるのが
「どんなメッセージを発信するのか?」ということです
今回は、コンテンツを作る時に知っておきたい
超基本を紹介していきます
2023年1月8日
2023年5月26日
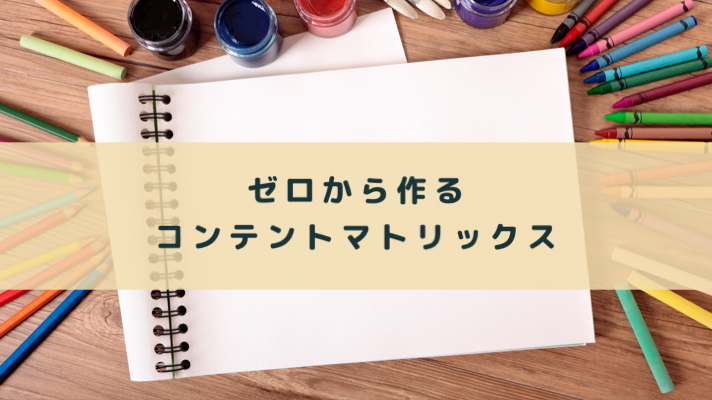
コンテンツ作成
ゼロから作る「コンテントマトリックス」
SNSなどのメディアを「ビジネスに繋げる」ことを目的にして
コンテントマトリックスの作り方をゼロから解説していきます
考えることも多く、時間もかかりますが
一度作ってしまえば、メディア運用がうんとはかどります!
2023年2月2日
2023年3月24日
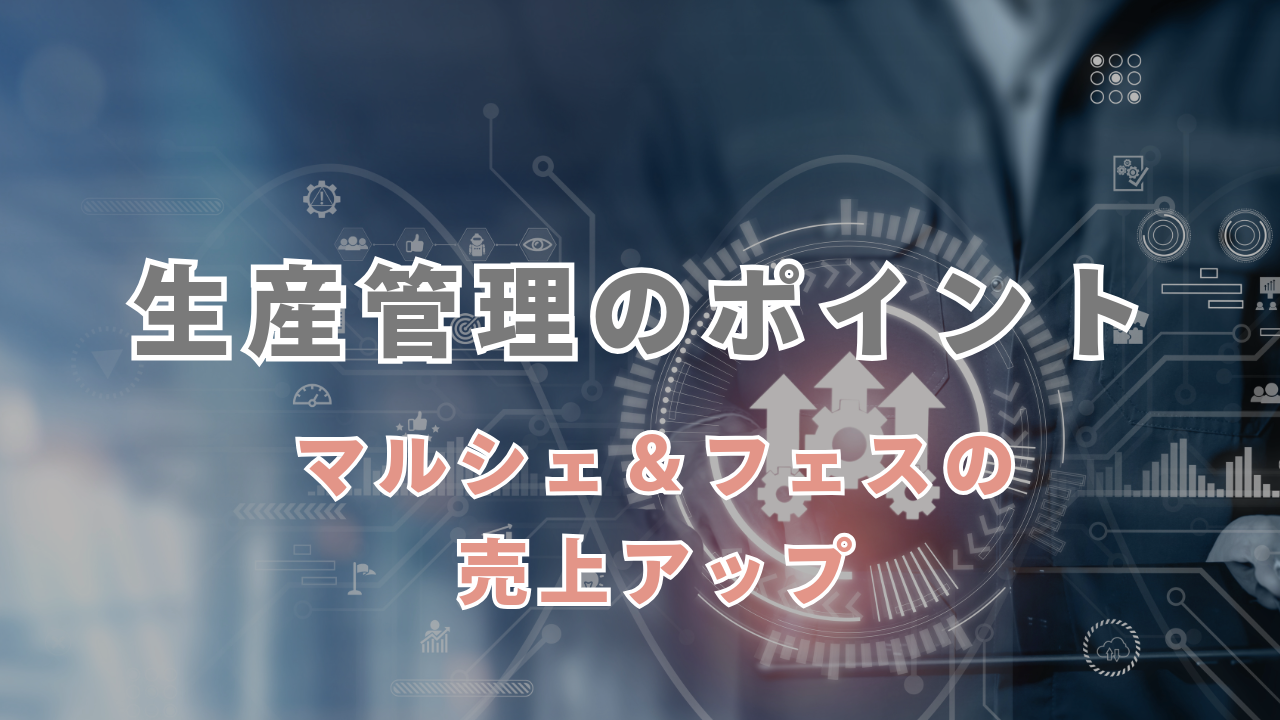

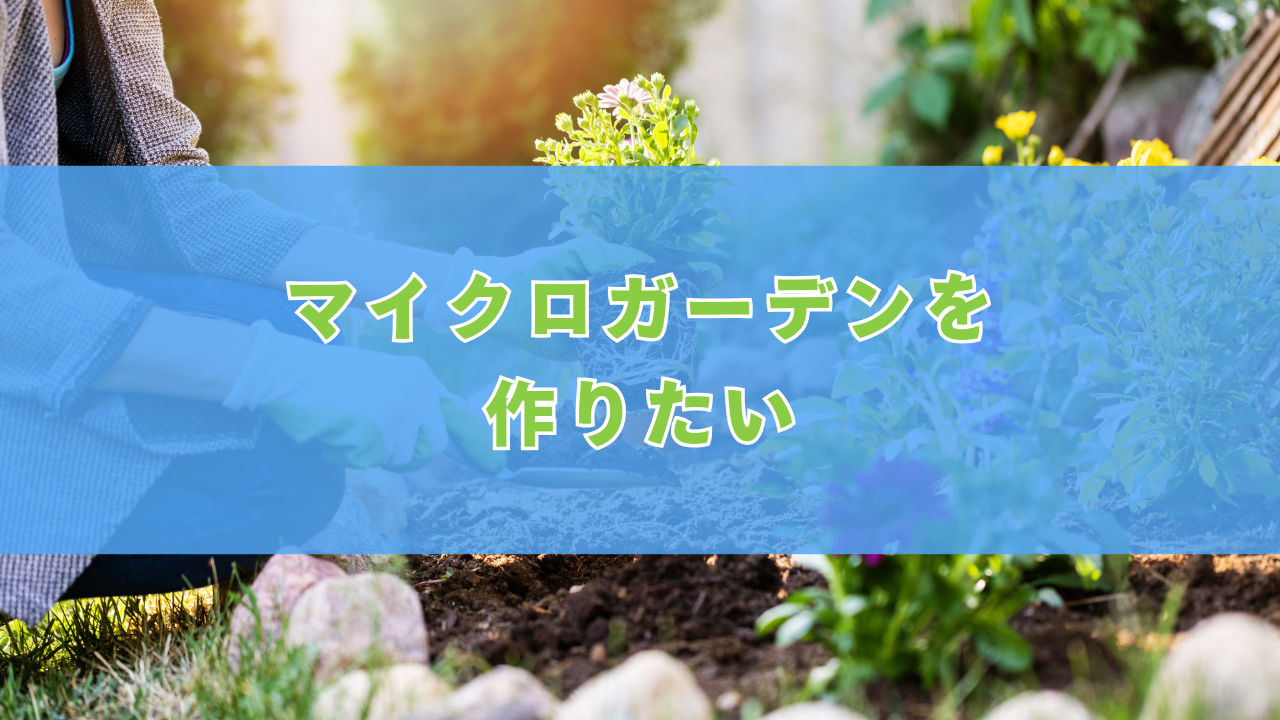
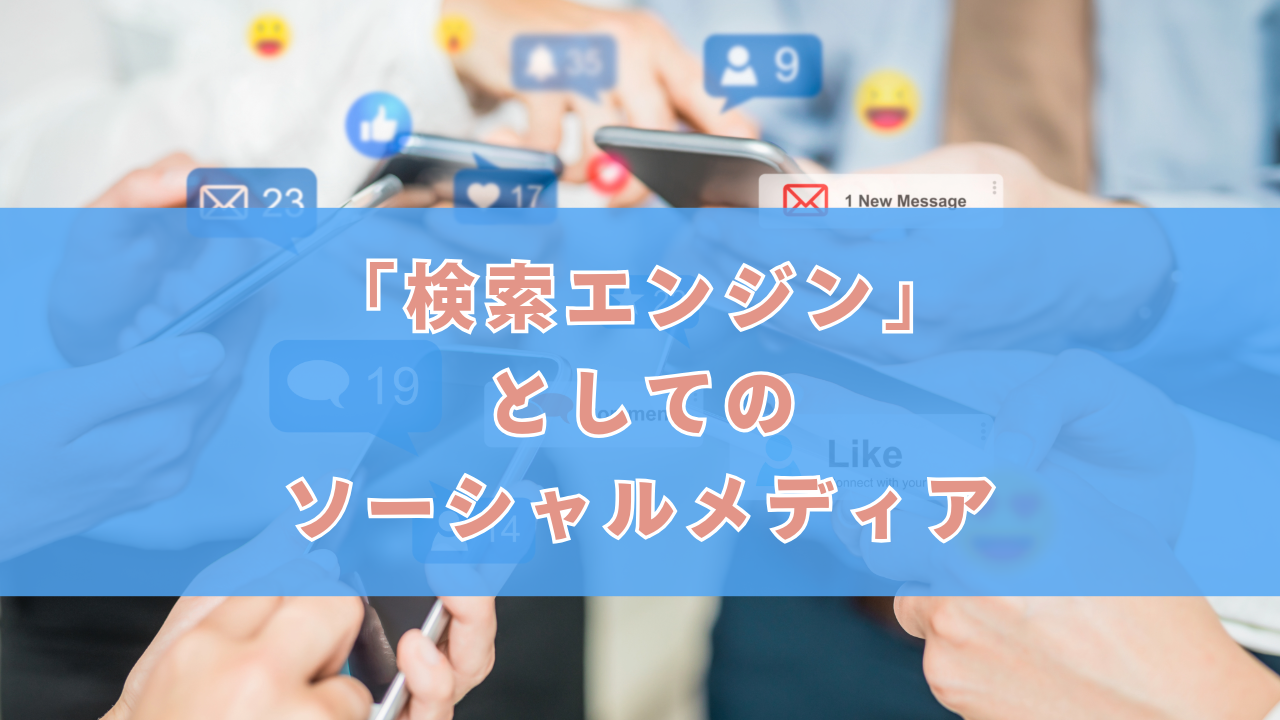


2件のフィードバック